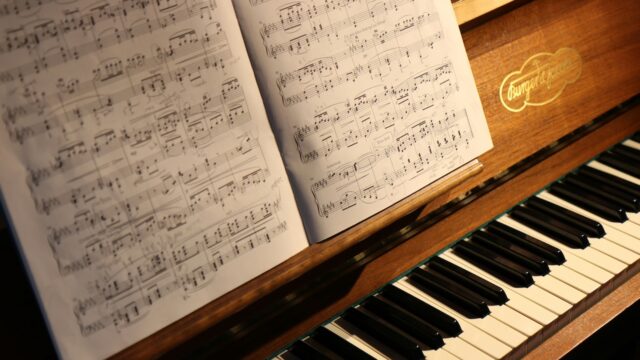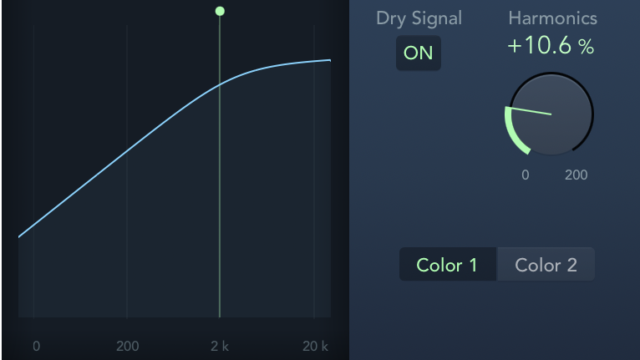リハーモナイゼーション(リハモ)は、既存のメロディーに新しいコード進行を付け直す技法です。この記事では、基本的な考え方から実践的なテクニックまで、具体例とともに解説します。
リハーモナイゼーションとは?基本概念の理解
リハーモナイゼーション(Reharmonization)は、メロディーはそのままに、コード進行を変更して新しい響きや雰囲気を作り出す技法です。ジャズで発展した技法ですが、現在では様々なジャンルで活用されています。
リハーモナイゼーションの主な目的
- 単調な進行に変化を加える
- 感情表現の幅を広げる
- ジャンルを超えたアレンジを可能にする
- 演奏者の個性を表現する
なぜリハーモナイゼーションが重要なのか
編曲や即興演奏において、リハーモナイゼーションはクリエイティビティを発揮する重要な手段です。同じメロディーでも、コード進行を変えることで全く違う印象の楽曲に生まれ変わらせることができます。
リハーモナイゼーションの基本原則
効果的なリハーモナイゼーションを行うには、いくつかの基本原則を理解する必要があります。
1. メロディーノートとの整合性
| ノートの種類 | 説明 | コードとの関係 |
|---|---|---|
| コードトーン | コードの構成音(1,3,5,7) | 必ず含める必要がある |
| テンション | 9,11,13度の音 | 適切なテンションとして扱う |
| パッシングノート | 経過音 | 短い音価なら無視可能 |
| アプローチノート | 目標音への導入音 | 解決先を考慮する |
2. 機能和声の維持または意図的な変更
リハーモナイゼーションでは、元のコード進行が持つトニック(T)、サブドミナント(SD)、ドミナント(D)の機能を理解し、それを維持するか意図的に変更するかを選択します。
基本的なリハーモナイゼーション技法
1. ダイアトニック代理(Diatonic Substitution)
トニック系: C → Am、Em
サブドミナント系: F → Dm、Am
ドミナント系: G → Bm♭5、Em
共通音を多く持つコードで置き換える最も基本的な技法です。
2. セカンダリードミナントの追加
元の進行: C – Am – Dm – G
リハモ後: C – A7 – Dm – D7 – G
各コードの前にそのコードへ向かうドミナント7thを挿入します。
3. トライトーン代理(Tritone Substitution)
基本原理: ドミナント7thコードを増4度(トライトーン)離れたドミナント7thで代理
例: G7 → D♭7
ジャズで頻繁に使用される洗練された技法です。
実践的なリハーモナイゼーション例
ここからは、実際の楽曲を例に、段階的にリハーモナイゼーションを施していきます。
例1:「きらきら星」のジャズアレンジ
原曲:
C – C – F – C | F – C – G – C
レベル1(基本的なリハモ):
Cmaj7 – Am7 – Dm7 – G7 | Fmaj7 – Em7 – Dm7 G7 – Cmaj7
レベル2(中級リハモ):
Cmaj7 – A7 – Dm7 – D♭7 | Cmaj7/E – E♭dim7 – Dm7 G7 – Cmaj7
レベル3(上級リハモ):
Cmaj7 – C#dim7 – Dm7 – D#dim7 | Em7 – E♭maj7 – Dm7 D♭7 – Cmaj7
例2:ポップスのR&B風リハーモナイゼーション
原曲: F – G – Em – Am
R&B風リハモ:
Fmaj9 – G13sus4 G13 – Em11 – Am9
↓
Fmaj7/A – G/B – Em7/G – Am7 Am7/D
スラッシュコードとテンションを加えることで、より洗練された響きになります。

高度なリハーモナイゼーション技法
1. クロマチックアプローチ
目標のコードに対して半音上または半音下から接近する技法です。
例:
元:C – F – G – C
リハモ:C – F#dim7 – F – G#dim7 – G – C#dim7 – C
2. コンスタントストラクチャー
同じコード品質(maj7、m7など)を平行移動させて進行を作る技法です。
例:
Cmaj7 – D♭maj7 – E♭maj7 – Emaj7 – Fmaj7
3. ペダルポイントとの組み合わせ
ベースノートを固定しながら上声部のハーモニーを変化させる
例(Cペダル):
C – C/E – C/F – C/G – C/A – C/B♭ – C
ジャンル別リハーモナイゼーションの特徴
ジャズ
ジャズリハモの特徴
- II-V-Iの多用
- 代理コードの積極的な使用
- 複雑なテンションの追加
- モーダルインターチェンジの活用
R&B/ソウル
R&B/ソウルリハモの特徴
- 拡張コード(9th、11th、13th)の多用
- スムーズなボイスリーディング
- ゴスペル由来の進行パターン
- クロマチックな内声の動き
ボサノバ
ボサノバリハモの特徴
- 洗練されたコードボイシング
- ♭5、#11などの特徴的なテンション
- 平行移動するコード進行
- 繊細な転回形の選択

DAWでのリハーモナイゼーション実践
効率的な作業フロー
- メロディートラックの分析 – キーとスケールを確認
- コードトラックの作成 – 元のコード進行を入力
- 複製トラックで実験 – 様々なリハモを試す
- A/B比較 – 原曲と聴き比べて選択
DAWでの便利な機能
- コードパッド機能でクイックに試行
- MIDIエフェクトでリアルタイム変換
- コードアシスタント機能の活用

リハーモナイゼーションの練習方法
初級編
- 童謡やフォークソングのコード付け替え
- 3コードの曲を4コード以上に拡張
- メジャーキーの曲をマイナーキーに変換(逆も)
中級編
- スタンダード曲のリハモ – ジャズスタンダードで練習
- ジャンル変換 – ポップスをジャズ風に、ジャズをR&B風に
- バッキングトラックの作成 – リハモした進行で伴奏作成
上級編
- 即興リハモ – リアルタイムでコード変更
- 複数バージョンの作成 – 同じ曲を5パターン以上リハモ
- オリジナル曲への応用 – 自作曲のセルフリハモ
よくある失敗と対処法
1. メロディーとの不協和
問題: リハモしたコードがメロディーと衝突する
対処法: メロディーノートを必ずコードトーンかテンションとして含める
2. 過度な複雑化
問題: コードが複雑すぎて原曲の良さが失われる
対処法: シンプルな部分も残し、メリハリをつける
3. 機能の喪失
問題: コード進行の推進力がなくなる
対処法: ケーデンス(終止形)は適切に配置する
実践例:アニソンのリハーモナイゼーション
アニソンは比較的シンプルなコード進行が多いため、リハーモナイゼーションの練習に最適です。
原曲: F – G – Em – Am
ジャズ風:
Fmaj7 – G7alt – Em7♭5 – A7alt – Am7
ネオソウル風:
Fmaj9#11 – G13sus4 – Em11 – Am9(add13)
まとめ:リハーモナイゼーションをマスターするために
リハーモナイゼーションは、音楽的創造性を高める強力なツールです。以下のステップで着実にスキルを向上させましょう。
マスターへの5つのステップ
- 基本的な代理コードを覚える
- 好きな曲で実践練習を重ねる
- 様々なジャンルのリハモを研究する
- 耳コピとアナライズを習慣化する
- 自分なりのリハモスタイルを確立する
リハーモナイゼーションは奥が深く、一朝一夕には身につきません。しかし、基本を理解し、継続的に練習することで、必ず自分のものにできます。まずは簡単な童謡から始め、徐々に複雑な楽曲へとステップアップしていきましょう。