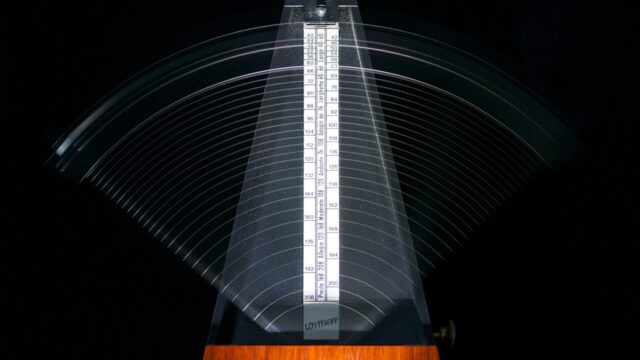DTMで音楽制作をしている皆さん、ミックスとマスタリングは楽曲のクオリティを左右する超重要な工程ですよね!「プロのサウンドに近づけたいけど、どうすればいいかわからない…」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、ミックスとマスタリングの裏技を余すところなくご紹介します。定番のテクニックから、ちょっとマニアックな裏技まで、あなたの楽曲を劇的に進化させるヒントが満載です!
ミックスの裏技
ミックスは、各トラックの音量バランス、定位、音色などを調整し、楽曲全体をまとめる工程です。ここでは、プロが実践しているミックスの裏技を、具体的な方法とともに解説します。
EQを使いこなす
EQは、特定の周波数帯域をブースト/カットすることで、音色を調整するエフェクトです。ミックスにおいて、EQは最も重要なツールの一つと言えるでしょう。
周波数帯域を意識する
特徴
- 各楽器には、それぞれ特徴的な周波数帯域があります。
- 例えば、キックドラムは低音域、スネアドラムは中音域、シンバルは高音域が中心です。
- これらの周波数帯域を意識してEQを調整することで、各楽器の音が分離し、クリアなミックスを実現できます。
使用例
キックドラムの低音域を少しブーストし、スネアドラムの中音域を少しカットすることで、キックとスネアの音がぶつからず、それぞれの音がより明確に聞こえるようになります。

不要な周波数をカットする
特徴
- 各トラックには、不要な低音域や高音域が含まれていることがあります。
- これらの不要な周波数をカットすることで、ミックス全体がスッキリし、音の分離が良くなります。
使用例
ボーカルトラックの100Hz以下をハイパスフィルターでカットすることで、低音域のノイズや部屋の反響音を軽減できます。
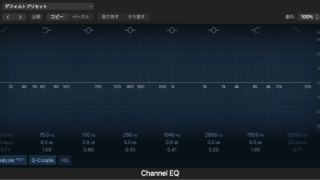
マスキングを避ける
複数のトラックで同じ周波数帯域が重なっていると、音が濁って聞こえる「マスキング」という現象が起こります。EQを使って、各トラックの周波数帯域を調整し、マスキングを避けるようにしましょう。
コンプレッサーを使いこなす
コンプレッサーは、音量のダイナミックレンジ(最も大きい音と最も小さい音の差)を圧縮するエフェクトです。コンプレッサーを適切に使うことで、音圧を上げ、迫力のあるサウンドを実現できます。
アタックタイムとリリースタイムを調整する
特徴
- アタックタイムは、コンプレッサーが音に反応するまでの時間です。
- リリースタイムは、コンプレッサーが元の状態に戻るまでの時間です。
- これらのパラメーターを調整することで、音の立ち上がりや余韻をコントロールできます。
使用例
スネアドラムのアタックタイムを短く、リリースタイムを長く設定することで、スネアのアタック感を強調しつつ、余韻を残すことができます。


サイドチェインコンプレッションを使う
サイドチェインコンプレッションは、あるトラックの音量を、別のトラックの音量に連動して変化させるテクニックです。例えば、キックドラムの音に合わせてベースの音量を下げることで、キックの音がより際立ち、グルーヴ感を強調できます。
リバーブとディレイを使いこなす
リバーブとディレイは、音に空間的な広がりや残響を加えるエフェクトです。これらのエフェクトを効果的に使うことで、楽曲に奥行きと立体感を与えることができます。
センド/リターンで使う
リバーブやディレイは、直接トラックにインサートするのではなく、センド/リターンで使うのが一般的です。センド/リターンを使うことで、複数のトラックに同じエフェクトを適用でき、CPU負荷を軽減できます。
プリディレイを調整する
特徴
- プリディレイは、原音と残響音の間にわずかな時間差を作るパラメーターです。
- プリディレイを調整することで、残響音の距離感や広がりをコントロールできます。
使用例
ボーカルトラックのプリディレイを長めに設定することで、ボーカルが空間の奥にいるような印象を与えることができます。
マスタリングの裏技
マスタリングは、ミックスされた音源を最終的な製品レベルに仕上げる工程です。ここでは、プロが実践しているマスタリングの裏技を、具体的な方法とともに解説します。
リファレンス音源と比較する
自分の楽曲と、プロの楽曲(リファレンス音源)を聴き比べながらマスタリングを行うことで、客観的な視点を持つことができます。音量、音圧、周波数バランスなどを比較し、自分の楽曲に足りない部分を見つけ、改善していきましょう。
マルチバンドコンプレッサーを使う
マルチバンドコンプレッサーは、周波数帯域ごとに異なるコンプレッション設定を適用できるエフェクトです。マルチバンドコンプレッサーを使うことで、より細かく音圧を調整できます。
使用例
低音域は強めにコンプレッションをかけ、中音域は軽めに、高音域はほとんどコンプレッションをかけない、といった使い方ができます。
リミッターを使いこなす
リミッターは、音量が一定のレベルを超えないように制限するエフェクトです。リミッターを使うことで、音割れを防ぎつつ、音圧を最大限に高めることができます。
リミッターをかけすぎると、音が潰れてしまい、ダイナミックレンジが失われてしまいます。リミッターは、あくまで最終的な音圧調整として、慎重に使いましょう。
ステレオイメージャーを使う
ステレオイメージャーは、音の左右の広がりを調整するエフェクトです。ステレオイメージャーを使うことで、楽曲の立体感を強調したり、特定の楽器を目立たせたりすることができます。
使用例
ボーカルトラックのステレオイメージを少し狭めることで、ボーカルを中央に定位させ、より力強く聞こえるようにすることができます。
メーターを活用する
特徴
- ピークメーター:音量の最大値を示します。クリッピング(音割れ)を防ぐために、ピークメーターが0dBを超えないように注意しましょう。
- RMSメーター:音量の平均値を示します。RMSメーターを参考にすることで、楽曲全体の音圧レベルを把握できます。
- ラウドネスメーター:人間の聴覚に基づいた音量レベルを示します。近年、音楽配信サービスではラウドネスノーマライゼーション(音量を自動的に調整する機能)が採用されているため、ラウドネスメーターを参考にマスタリングを行うことが重要です。


まとめ
この記事では、DTMにおけるミックスとマスタリングの裏技をご紹介しました。これらのテクニックを参考に、あなたの楽曲をプロレベルのサウンドに近づけてください!
もちろん、今回ご紹介した裏技はほんの一部です。DTMの世界は奥深く、常に新しいテクニックやツールが登場しています。ぜひ、色々な情報を収集し、自分なりのミックス&マスタリング術を確立してくださいね!