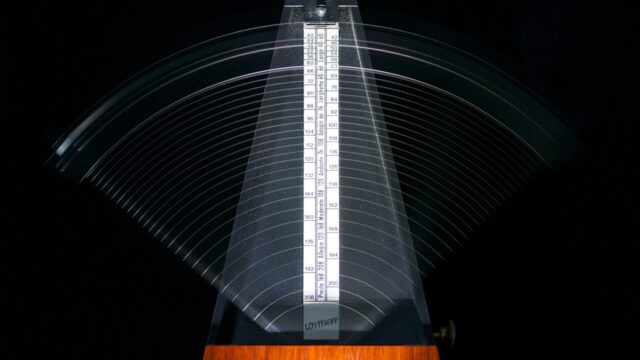DTM(デスクトップミュージック)でオリジナル曲を作ってみたい!そう思ってDAW(Digital Audio Workstation)ソフトや機材を揃えたものの、「何から手をつけていいかわからない」「アイデアが浮かばない」「途中で挫折してしまう」…そんな悩みを抱えていませんか?
かつては専門的な知識や高価な機材が必要だった作曲も、今やパソコン一台あれば誰でも始められる時代になりました。しかし、自由度が高い反面、選択肢の多さに戸惑い、なかなか曲を完成させられないという方も少なくありません。
こんにちは!音楽とDTMをこよなく愛するブロガー兼WEBマーケターです。これまで様々なDAWに触れ、多くの作曲テクニックを学んできました。この記事では、そんな私の経験に基づき、DTM初心者の方が作曲の壁を乗り越え、スムーズに曲作りを進めるためのシンプルなコツを厳選してご紹介します。
難しい音楽理論や高度なテクニックは一旦置いておいて、まずは「曲を完成させる」楽しさを体験してみませんか?この記事を読めば、あなたもきっと作曲のスピードが上がり、DTMがもっと楽しくなるはずです。
作曲の壁にぶつかる前に知っておきたい心構え
具体的なテクニックに入る前に、DTM作曲に取り組む上での心構えについてお話しします。実は、技術的な問題よりも、メンタル面が原因で挫折してしまうケースは非常に多いのです。
完璧主義を捨てる勇気
最初から完璧な曲を作ろうとしていませんか?「プロみたいなクオリティじゃないとダメだ」「もっと良いメロディがあるはずだ」と考え始めると、手が止まってしまいがちです。
最初から100点満点を目指さないこと。まずは60点、いや、40点でも良いので、「形にする」ことを意識しましょう。完成度が低くても、一曲完成させたという経験は、大きな自信と次へのモチベーションに繋がります。
名だたる作曲家たちも、最初から名曲ばかりを生み出していたわけではありません。数多くの試行錯誤、失敗作の上に、素晴らしい作品が成り立っているのです。
まずは「完成させる」ことを目標に
作曲を始めたばかりの頃は、とにかく「最後まで作り上げる」経験を積むことが重要です。途中で「これはダメだ」と思っても、投げ出さずに最後まで進めてみましょう。
イントロ、Aメロ、Bメロ、サビ、アウトロといった基本的な構成を意識し、たとえ短い曲でも良いので、一つの作品として完結させることを目標にします。
曲の構成がわからない場合は、好きな曲を参考にしてみましょう。どの部分がAメロで、どこからがサビなのかを分析するだけでも、構成の感覚が掴めてきます。
完成させた曲は、後からいくらでも修正できます。まずは「完成」というゴールテープを切る達成感を味わうことが、継続の秘訣です。
好きな曲を徹底的に分析する
「どんな曲を作りたいか」というイメージを持つことは非常に大切です。そのために、自分が好きな曲、目標とする曲(リファレンス曲)を徹底的に分析してみましょう。
以下の点を意識して聴いてみてください。
分析ポイントの例:
- 曲の構成(イントロ、メロ、サビなど)
- 使われている楽器とその役割
- コード進行
- メロディラインの特徴
- リズムパターン
- 曲全体の雰囲気や世界観
- ミックス(各楽器の音量バランスや定位)
DAWに取り込んで波形を見ながら分析するのも効果的です。耳コピ(聴き取って再現すること)に挑戦してみるのも、非常に良い練習になります。完全に再現できなくても、その過程で多くの発見があるはずです。
分析する際は、「良い/悪い」で判断するのではなく、「なぜ自分はこの曲が好きなのか」「どんな要素が心地よく感じるのか」を客観的に探るようにしましょう。
DTM作曲を加速させるシンプルなテクニック【実践編】
ここからは、具体的な作曲テクニックをご紹介します。どれもシンプルで、すぐに試せるものばかりです。ぜひ、あなたの作曲に取り入れてみてください。
テクニック1: ループ素材を積極的に活用する
「ループ素材を使うのは手抜きでは?」と感じる方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。ループ素材は、作曲のスピードを劇的に向上させ、アイデアのきっかけを与えてくれる強力なツールです。
ループ素材のメリット:
- ドラムパターンやベースラインなどを素早く構築できる
- 自分では思いつかないようなフレーズに出会える
- 曲の土台を簡単に作れる
- クオリティの高いサウンドを手軽に導入できる
ループ素材のデメリット:
- オリジナリティを出しにくい場合がある
- ループ感(繰り返し感)が強くなりすぎることがある
- 自分のイメージに合う素材を探すのに時間がかかることがある
ループ素材は、DAWに付属しているものや、専用のサービスから入手できます。
ループ素材の探し方(代表的なサービス):
- Splice (スプライス): https://splice.com/
膨大な量のループ素材やワンショットサンプルを月額料金で利用できる定番サービス。ジャンルや楽器、キー、BPMなどで絞り込み検索が可能です。 - Loopcloud (ループクラウド): https://www.loopcloud.com/
こちらも人気のサブスクリプションサービス。専用ソフト上でDAWと連携し、キーやテンポを自動で合わせて試聴できるのが便利です。 - Sample Tools by Cr2: https://www.sampletoolsbycr2.com/
高品質なサンプルパックを販売。ジャンルに特化したパックが多いのが特徴です。
多くのサービスで無料サンプルが提供されています。まずは無料のものを試してみて、サービスの使い勝手や素材のクオリティを確認してみましょう。
ループ素材をそのまま使うだけでなく、一手間加えることでオリジナリティを出すことも可能です。
ループ素材の加工テクニック例:
- スライスして並び替える: リズムやフレーズを変化させる
- ピッチ(音程)を変える: 曲のキーに合わせたり、雰囲気を変えたりする
- フィルターやエフェクトをかける: 音色を加工する(例:ローファイにする、ディレイをかける)
- 他のループ素材と組み合わせる: 複数の素材をレイヤーして新しいグルーヴを作る
テクニック2: プリセット音源を起点にする
シンセサイザーやドラムマシンなどのソフトウェア音源には、多くの場合、あらかじめ調整された「プリセット」が多数収録されています。
音作りはDTMの醍醐味の一つですが、初心者にとってはハードルが高い部分でもあります。「どんな音色を使えばいいかわからない」という場合は、まずプリセットを積極的に活用しましょう。
プリセット活用のメリット:
- すぐにイメージに近い音色を見つけられる
- プロが作った質の高いサウンドを使える
- 音作りの知識がなくても、多彩な音色を試せる
- プリセットを分析することで音作りの勉強になる
プリセット選びのコツ:
- 曲のジャンルや雰囲気に合ったカテゴリから探す(例:Pad, Lead, Bass, Pluckなど)
- キーワード検索を活用する(例:”Bright”, “Dark”, “80s”, “Ambient”など)
- とりあえず色々なプリセットを試聴してみる
- 「お気に入り」機能があれば、よく使うプリセットや気に入ったプリセットを登録しておく
気に入ったプリセットが見つかったら、そのまま使うだけでなく、少しだけパラメータを調整してみるのがおすすめです。
プリセットを自分流にカスタマイズする方法例:
- フィルターのカットオフやレゾナンスを調整する: 音の明るさやクセを変える
- エンベロープ(ADSR)を調整する: 音の立ち上がりや長さを変える
- LFOの深さや速さを変える: 音に揺らぎを加える
- 内蔵エフェクト(リバーブ、ディレイ、コーラスなど)のかかり具合を調整する: 空間的な広がりや質感を調整する
少し調整するだけでも、既成のプリセット感が薄れ、曲への馴染みが良くなります。パラメータの意味がわからなくても、まずは色々いじってみて、音の変化を楽しむことから始めましょう。
テクニック3: 定番コード進行を使ってみる
「コード進行が思いつかない」という悩みも、作曲初心者にはよくある壁です。そんな時は、世の中の名曲で使われている「定番コード進行」を拝借してみましょう。
定番コード進行は、多くの人に心地よく響く、いわば「黄金パターン」です。これを土台にすることで、スムーズにメロディや他のパートを組み立てていくことができます。
代表的な定番コード進行:
- カノン進行 (C→G→Am→Em→F→C→F→G): パッヘルベルのカノンで有名な進行。J-POPでも頻繁に使われます。感動的、壮大な雰囲気を出しやすいです。
- 王道進行/小室進行 (F→G→Em→Am): 90年代のヒット曲に多用された進行。疾走感、切なさを表現しやすいです。(キーがCの場合。F→G→Cというパターンも多い)
- 丸の内進行/Just The Two of Us進行 (Fmaj7→E7→Am7→C7 など): オシャレで都会的な雰囲気を持つ進行。AORやネオソウルなどでよく使われます。(キーによってコードの種類は変わります)
- 循環コード (例: C→Am→Dm→G): 4つのコードを繰り返すシンプルな進行。様々なジャンルで応用されています。


これらのコード進行はあくまで一例です。キーを変えたり、一部のコードを変えたり、セブンスコードやテンションコードを加えたりすることで、バリエーションは無限に広がります。
コード進行を探すのに便利なWebサイトもあります。
- Hooktheory Trends: https://www.hooktheory.com/trends
ヒット曲で使われているコード進行を分析、検索できるサイト。進行パターンから曲を探したり、曲から進行を調べたりできます。(英語サイトですが、非常に参考になります) - その他、日本語でも「コード進行 解析」「定番コード進行」などで検索すると、多くの解説サイトが見つかります。
コード進行が決まったら、そのコードに合わせて鼻歌でメロディを歌ってみたり、MIDIキーボードで音を探ってみたりしましょう。コード構成音を中心にメロディを作ると、自然に響きやすいです。
DAWによっては、コードトラック機能やコード支援機能が搭載されているものもあります。これらを活用するのも有効な手段です。
テクニック4: リファレンス曲を設定する
心構えの部分でも触れましたが、「こんな曲を作りたい」という目標となるリファレンス曲を設定することは、作曲プロセス全体を通して非常に有効です。
リファレンス曲とは?
自分が作りたい曲のイメージに近い、既存の楽曲のことです。ジャンル、雰囲気、サウンド感、構成など、何かしらの要素を参考にする対象となります。
リファレンス曲の選び方:
- 純粋に「好き」な曲
- 作りたいジャンルの代表的な曲
- 特定のサウンド(ドラムの音、シンセの音色など)が理想的な曲
- 曲の構成が参考になる曲
複数曲を設定してもOKです。「この曲のドラムパターンと、あの曲のシンセの雰囲気を参考にしよう」といった使い方もできます。
リファレンス曲の分析ポイント:
- 曲の構成: 各セクションの長さ、展開の仕方
- 使用楽器とアレンジ: 各楽器がどんな役割を果たしているか
- サウンドデザイン: 音色の特徴、エフェクトの使い方
- ミックスバランス: 各楽器の音量、定位(左右の配置)、奥行き
- ダイナミクス: 曲全体の音量の変化、盛り上がり方
使用例:DAWのプロジェクト内にリファレンス曲のオーディオファイルを読み込んで、いつでも聴き比べられるようにしておくと便利です。波形を見ながら構成を分析したり、スペクトラムアナライザーを使って周波数特性を比較したりするのも良いでしょう。
リファレンス曲はあくまで「参考」にするものです。完全にコピーするのではなく、良いと思った要素を自分の曲にどう取り入れるかを考えましょう。丸パクリは著作権侵害になる可能性もあります。
テクニック5: テンプレートを活用する
毎回ゼロからトラックを作成し、音源やエフェクトを立ち上げ、ルーティングを設定するのは意外と時間がかかる作業です。そこで役立つのが「テンプレート」機能です。
テンプレートとは、よく使うトラック構成、音源、エフェクト、ルーティング設定などを保存しておき、新しいプロジェクトを開始する際に呼び出せる機能のことです。
テンプレートのメリット:
- 作曲を始めるまでの準備時間を大幅に短縮できる
- 毎回同じ設定をする手間が省ける
- 自分の基本的な制作環境を統一できる
- アイデアが浮かんだ時にすぐに音を出し始められる
テンプレートの作成方法(一般的な例):
- 空のプロジェクトを開く
- よく使う楽器トラック(ドラム、ベース、ピアノ、シンセなど)を作成する
- 各トラックによく使う音源やエフェクト(EQ、コンプレッサーなど)をインサートする
- よく使うセンドエフェクト(リバーブ、ディレイなど)用のFXトラック(またはAUXトラック)を作成し、ルーティングを設定する
- 必要であれば、マーカートラックで基本的な曲構成(Intro, Verse, Chorusなど)の目安を入れておく
- DAWの「テンプレートとして保存」機能を使って保存する
最初はシンプルなテンプレートから始め、作曲を進める中で「これもよく使うな」と思った設定を随時追加・更新していくのがおすすめです。ジャンルごとにテンプレートを複数作成しておくのも良いでしょう。
多くのDAWには、最初から様々なジャンル向けのテンプレートが付属しています。また、プロのクリエイターが作成したテンプレートが販売・配布されている場合もあります。これらを参考に、自分のテンプレートを構築していくのも効率的です。
さらに作曲スピードを上げるためのヒント
上記のテクニックに加えて、日々の作業効率を上げるためのヒントをいくつかご紹介します。
ショートカットキーを覚える
DAWの操作は、マウスだけでなくショートカットキーを積極的に使うことで格段にスピードアップします。再生・停止、録音、コピー&ペースト、ズームイン・アウト、ミキサー表示など、頻繁に使う操作のショートカットキーは優先的に覚えましょう。
最初は少し面倒に感じるかもしれませんが、慣れれば無意識に指が動くようになり、思考を止めずに作業を進められます。DAWの取扱説明書やヘルプ、Webサイトなどでショートカット一覧を確認できます。

定期的にDAWやプラグインの情報を収集する
DTMの世界は日進月歩です。新しいDAWのバージョンアップ、便利なプラグインの登場、新しいテクニックやトレンドなど、常に新しい情報にアンテナを張っておくことも大切です。
信頼できる音楽情報サイトやブログ、YouTubeチャンネル、SNSなどをチェックして、最新情報を収集する習慣をつけましょう。新しいツールやテクニックが、あなたの作曲プロセスを劇的に改善してくれるかもしれません。
- Sound On Sound: https://www.soundonsound.com/ (英語ですが、質の高いレビューや技術記事が多い)
- MusicRadar: https://www.musicradar.com/ (ニュース、レビュー、チュートリアルなど幅広くカバー)
- 国内のDTM情報サイトや個人のブログも多数あります。
作曲仲間を見つける・コミュニティに参加する
一人で黙々と作業するのも良いですが、同じ目標を持つ仲間と交流することで、モチベーション維持や新たな発見に繋がります。
SNSやオンラインコミュニティ、音楽系のイベントなどで作曲仲間を見つけ、お互いの曲を聴かせ合ったり、情報交換したりするのは非常に有益です。他の人の作品や制作環境を知ることで、刺激を受け、自分の視野も広がります。
AI作曲支援ツールを試してみる
近年、AI(人工知能)技術を活用した作曲支援ツールも登場しています。メロディやコード進行、ドラムパターンなどを自動生成してくれるツールは、アイデア出しのきっかけや、マンネリ打破に役立つ可能性があります。
代表的なものには以下のようなサービスがありますが、サービスの形態変更や終了も起こりうるため、最新情報を確認してください。
- AIVA: https://www.aiva.ai/ (クラシックから現代音楽まで、様々なスタイルの曲を生成)
- DAWやプラグインにAI機能が搭載されるケースも増えています。(例: Logic ProのDrummer、iZotope NeutronのAssistant機能など)
AIツールはあくまで「支援」ツールです。生成されたものをそのまま使うだけでなく、それを元に自分で編集・加工していくことで、よりオリジナリティのある作品に昇華させることができます。
おすすめDAWとプラグイン情報 (2025年版)
これからDTMを始める方や、新しいツールを探している方向けに、いくつか代表的なDAWと、作曲を助けるおすすめプラグインをご紹介します。(2025年時点の情報です)
初心者向けDAW紹介
多くのDAWには、機能制限版や廉価版が用意されており、初心者でも手軽に始めやすくなっています。
- Steinberg Cubase Elements: https://www.steinberg.net/ja/cubase/
総合的な機能が高く、プロにも愛用者が多いDAWの入門版。コードトラック機能などが作曲に便利。Windows/Mac対応。 - PreSonus Studio One Artist: https://www.presonus.com/ja/studio-one
比較的新しいDAWながら、直感的な操作性で人気。ドラッグ&ドロップ中心のワークフローが特徴。Windows/Mac対応。無料版 (Studio One Prime) もあります。 - Image-Line FL Studio Fruity Edition: https://www.image-line.com/fl-studio/
EDMやヒップホップ系のクリエイターに人気。ステップシーケンサーが特徴的。ライフタイムフリーアップデート(一度購入すれば将来のバージョンアップが無料)が魅力。Windows/Mac対応。 - Apple Logic Pro: https://www.apple.com/jp/logic-pro/
Macユーザー限定ですが、比較的安価ながら高機能。豊富な音源やループ素材が付属し、初心者でも始めやすい。 - Ableton Live Intro: https://www.ableton.com/ja/live/
ライブパフォーマンスにも強いDAWの入門版。セッションビューという独自の機能がアイデアスケッチに便利。Windows/Mac対応。
無料体験版があるDAWも多いので、実際に触ってみて、自分に合ったものを選ぶのが一番です。
以下の記事で16個の無料DAWを記事にしています

作曲を助けるおすすめプラグイン
DAW付属の音源やエフェクトも優秀ですが、サードパーティ製のプラグインを追加することで、さらに音作りの幅が広がります。
- Native Instruments Komplete Start: https://www.native-instruments.com/jp/products/komplete/bundles/komplete-start/get-komplete-start/
無料で入手できる音源・エフェクトバンドル。シンセ、サンプリング音源、エフェクトなど、即戦力になるものが多数収録されています。まずはここから試すのがおすすめ。 - Spitfire Audio LABS: https://labs.spitfireaudio.com/
こちらも無料。高品質なオーケストラ音源やピアノ、実験的なサウンドなど、個性的なライブラリが定期的に追加されます。 - Xfer Records Serum: https://xferrecords.com/products/serum/
EDMシーンを中心に絶大な人気を誇るウェーブテーブルシンセサイザー。非常に多機能で、音作りの自由度が高いです。(有料) - Toontrack EZdrummer / Superior Drummer: https://www.toontrack.com/
リアルなドラムサウンドを求めるなら定番のドラム音源。豊富なMIDIグルーヴ(ドラムパターン)が付属し、簡単にリアルなドラムトラックを作成できます。(有料) - iZotope Ozone Elements / Neutron Elements: https://www.izotope.com/ja.html
AIによるアシスタント機能が搭載されたマスタリング/ミキシングプラグイン。初心者でも手軽に音圧やバランスを整えることができます。(有料ですが、セールで安くなることも多い)
まとめ:シンプルなコツを実践して、作曲を楽しもう!
今回は、DTM初心者の方が作曲を加速させるためのシンプルなコツをご紹介しました。
今回紹介した主なコツ:
- 心構え: 完璧主義を捨て、まずは完成させることを目標にする。好きな曲を分析する。
- テクニック: ループ素材、プリセット音源、定番コード進行、リファレンス曲、テンプレートを活用する。
- 効率化: ショートカットキーを覚える、情報収集を怠らない、仲間を見つける、AIツールを試す。
最初から複雑なことをやろうとせず、まずはこれらのシンプルな方法を試してみてください。一つ一つのハードルが下がり、曲作りのプロセスがスムーズに進むようになるはずです。
何よりも大切なのは、楽しみながら継続することです。今回ご紹介したコツが、あなたのDTMライフをより豊かに、そしてクリエイティブにする一助となれば幸いです。
さあ、DAWを開いて、あなたの音楽を形にしてみましょう!